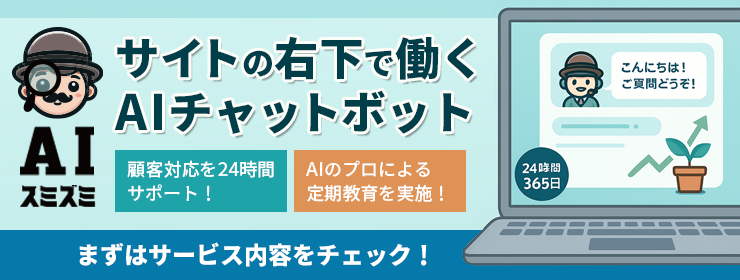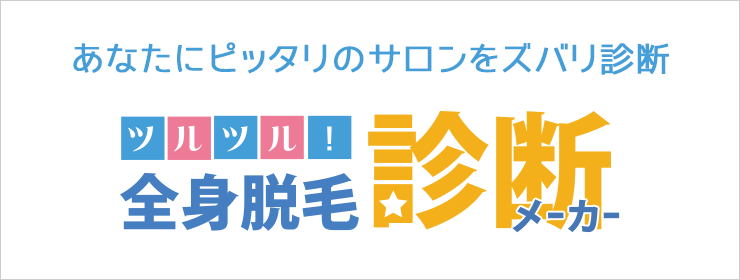BLOGブログ

目次

なぜ今「法人向けAIツール」なのか?
2023年以降、ChatGPTをはじめとした生成AIの急速な普及により、企業の現場にもAIの導入が加速しています。しかし、その一方で「ツールは入れたけれど、使われていない」「成果につながらない」といった声が増えてきました。
その原因は明確です。従来の汎用AIツールは、あくまで“個人向け”を想定しており、業務プロセスに即した設計にはなっていないからです。こうした背景から今、多くの企業が注目しているのが、法人向けに設計されたAIツールです。
たとえば、JAPAN AIは、社内マニュアルやFAQと連携し、「質問すれば即答してくれる社内ヘルプデスク」のような環境を実現しています。RAG(Retrieval Augmented Generation)技術により、ナレッジを引き出すAIとして多数の導入実績を持ちます。
また、オートロンは、80種類以上の定型業務アシスタントを備え、プロンプト操作を不要とするUI設計が特徴です。SlackやGoogle Workspace、kintoneなどとの連携機能も豊富で、社内定着を見据えたテンプレート型の法人向けAIツールとして評価されています。
こうしたツールが支持される理由は明確です。「生成する」だけでなく、「業務に根付かせる」という視点を持っているからです。
実際に、私が関わってきたAI導入支援でも、成果が出ている企業には共通点があります。それは、ツールそのものではなく、導入後の運用フローまで見据えた戦略設計ができているということです。
なお、法人導入におけるよくある失敗パターンと、その回避方法については、以下の記事でも詳しく解説しています。
▶ 生成AI導入の落とし穴とは?失敗しないための選定基準と注意点
JAPAN AIは、RAG(情報拡張検索)を活用して、自社内のナレッジを活かしたチャットAIを構築できます。Excelのマクロ作成や議事録の自動化といった、実務に即した用途が多くの企業で評価されています。
オートロンは、すでに業務化されたAIアシスタントが80種類以上用意されており、プロンプトを書く必要がない点が大きな特徴です。SlackやGoogleカレンダーなどの業務アプリと連携して、定型業務を自動化できます。
一方で、通話データ分析に強いRevComm(MiiTel)や、コールセンター・業務ナレッジ支援に強いPKSHA AIなど、特定領域に特化したソリューションも存在します。
自社の課題に合わせて、「どの工程をAIで支援すべきか」「誰が使うのか」を明確にしたうえで選定を進めましょう。
▼JAPAN AI – 総合型AIプラットフォームの旗手

日本企業に最適化された法人向け生成AIプラットフォームとして、JAPAN AIは急速に注目を集めています。その最大の特徴は、単なる文章生成にとどまらず、マーケティング、営業支援、社内業務支援まで幅広くカバーする多層的なAI群を提供している点です。
主なプロダクトは「JAPAN AI CHAT」「JAPAN AI MARKETING」「JAPAN AI SPEECH」の3本柱で構成されています。
- JAPAN AI CHAT:業務フローに合わせたカスタマイズが可能な高精度チャットAI。RAGによる社内ナレッジ検索、FAQ対応などが可能です。
- JAPAN AI MARKETING:ペルソナ設定や広告文作成、画像生成からリーガルチェックまで、マーケティング業務を統合的に支援。
- JAPAN AI SPEECH:94%以上の精度で文字起こしを実現する音声認識AI。要約・話者識別・専門用語登録など、議事録作成に強み。
導入事例も豊富で、たとえばマーケティング支援企業では、広告の設問設計が1時間→15分に短縮され、担当者の熟練度に左右されない業務体制が実現しました。また、サービス業では、100件超の打ち合わせの議事録作成をAIが代行し、月20時間以上の工数削減を達成しています。
JAPAN AIが「旗手」と呼ばれる理由は、その多機能性だけでなく、業種別の課題に合わせた柔軟なカスタマイズ力にあります。加えて、導入支援チームがつくことで、単なるAI導入ではなく、「定着させるまでを伴走する」仕組みが整っているのも特徴です。
プロンプトの調整支援や、外部ツールとの柔軟な連携(SFA、CRMなど)も可能なことから、本格的に業務プロセスを変えたい企業にとっては、最有力候補のひとつとなるでしょう。
▼Autoron(オートロン)– AIアシスタントテンプレートの決定版
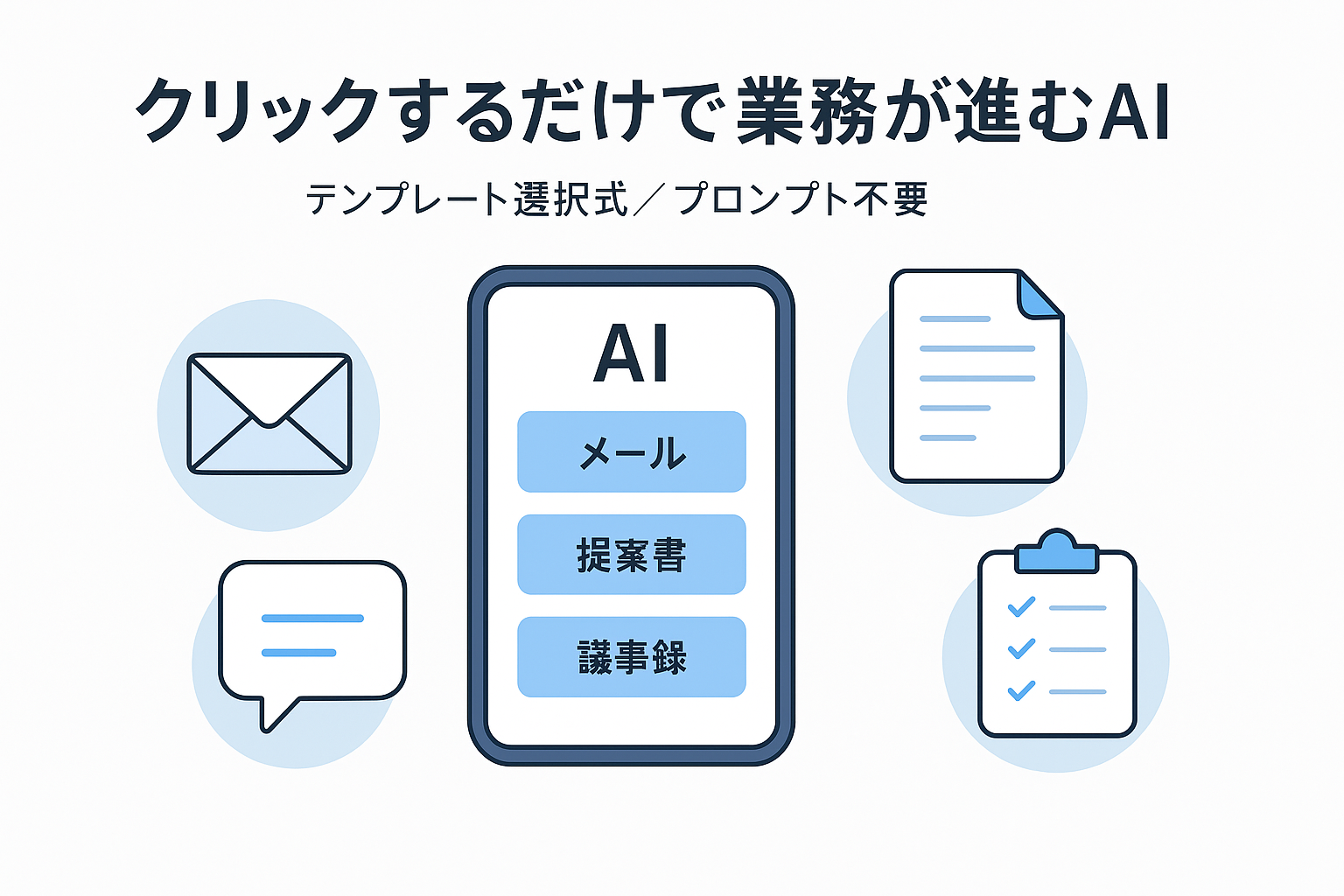
「誰でもすぐに、業務でAIを使える」——そんな発想を体現しているのが、オートロンです。提供元は東証グロース上場企業のランサーズ株式会社。法人向け生成AIツールの中でも、圧倒的な“導入ハードルの低さ”と“実行力”を兼ね備えたサービスです。
オートロンの最大の特徴は、約80種類以上の定型業務アシスタントがあらかじめ搭載されており、プロンプトを書く必要すらない点にあります。社内FAQ回答、議事録作成、メール文生成、Excel関数の解説、求人票の自動作成など、使いたい機能を選ぶだけで、誰でも業務にAIを取り入れることができます。
また、SlackやGoogleカレンダー、kintoneなどの業務ツールとも連携可能で、ワークフローとしての“自動実行”まで設計できるのもポイント。AIが「返答する」だけでなく、「作業をする」レベルに進化しています。
料金体系も非常に柔軟で、1アカウント月額2,000円(チケット制)。ChatGPT for Teamsの半額以下で運用可能なため、コストパフォーマンスにも優れています。
導入事例としては、ランサーズ社内のSRE部門において、設計支援・ログ分析・報告書作成・提案書の壁打ちなど多岐に渡る活用で、月30日分の作業が10日間削減されたという結果も出ています。
さらに、オンボーディングをスムーズにするための導入支援オプションもあり、生成AIの定着までを支援する体制も万全。技術的な知識がなくても、業務現場で確実に使えるAIツールを探している企業には、非常に相性が良い選択肢です。
▼exaBase 生成AI – セキュアな根拠付き出力で高信頼

「AIの回答に、根拠が必要」──そう考える企業に選ばれているのが、exaBase 生成AIです。提供元は東証プライム上場のエクサウィザーズ社で、もともと医療・介護・製造などの社会課題解決型AIを手掛けてきた実績があります。
exaBase 生成AIは、ユーザーからの質問に対して、回答とあわせて“根拠となる資料”を自動添付できる点が最大の特徴。これにより、意思決定や社内稟議において「なぜその回答なのか」を説明しやすくなり、業務におけるAI利用の透明性が確保されます。
また、処理は日本国内で完結し、社内アクセス制限やデータ保持設定も細かく可能。データがAIの学習に使われない仕様になっており、金融・保険・医療・官公庁など、高セキュリティ要件を持つ組織での導入が進んでいます。
部署単位・プロジェクト単位でのデータ閲覧権限を設定できるため、組織規模の大きい企業でも横断的な活用がスムーズ。また、出力形式も議事録、報告書、メール、説明資料など多岐に渡り、実際の業務文書としてすぐ使える品質を誇ります。
「AIを使っていること自体がリスクになるのでは?」と感じる企業にとって、exaBaseはまさに“信頼を担保しながら導入できるAI”の代表格です。特に法務、財務、IR、医療情報管理など、正確性と検証性が求められる現場でその真価を発揮します。
▼exaBase 生成AI – セキュアな根拠付き出力で高信頼

「AIの回答に、根拠が必要」──そう考える企業に選ばれているのが、exaBase 生成AIです。提供元は東証プライム上場のエクサウィザーズ社で、もともと医療・介護・製造などの社会課題解決型AIを手掛けてきた実績があります。
exaBase 生成AIは、ユーザーからの質問に対して、回答とあわせて“根拠となる資料”を自動添付できる点が最大の特徴。これにより、意思決定や社内稟議において「なぜその回答なのか」を説明しやすくなり、業務におけるAI利用の透明性が確保されます。
また、処理は日本国内で完結し、社内アクセス制限やデータ保持設定も細かく可能。データがAIの学習に使われない仕様になっており、金融・保険・医療・官公庁など、高セキュリティ要件を持つ組織での導入が進んでいます。
部署単位・プロジェクト単位でのデータ閲覧権限を設定できるため、組織規模の大きい企業でも横断的な活用がスムーズ。また、出力形式も議事録、報告書、メール、説明資料など多岐に渡り、実際の業務文書としてすぐ使える品質を誇ります。
「AIを使っていること自体がリスクになるのでは?」と感じる企業にとって、exaBaseはまさに“信頼を担保しながら導入できるAI”の代表格です。特に法務、財務、IR、医療情報管理など、正確性と検証性が求められる現場でその真価を発揮します。
▼Graffer AI Studio – ノーコードで部署特化業務を実装
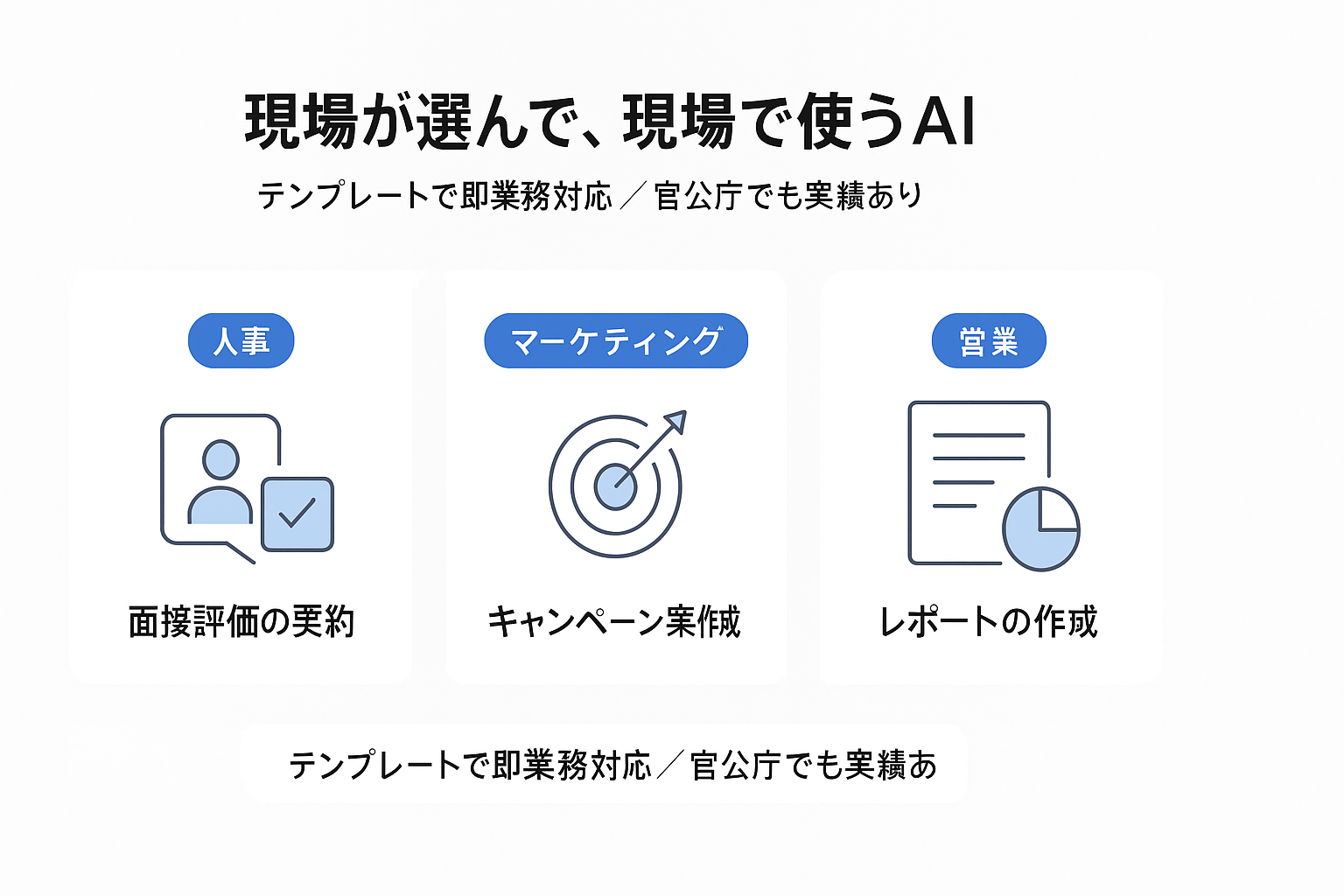
AIツールの社内定着において、大きな障壁となるのが「現場が使いこなせない」という課題です。その解決策として評価されているのが、Graffer AI Studioです。
Grafferは、もともと官公庁向けのデジタル化支援で高い実績を持つ企業であり、その技術と知見をもとに開発されたGraffer AI Studioは、プロンプト不要・ノーコードで利用できる“業務実装前提の生成AI”です。
最大の特徴は、部署ごとに用意されたテンプレートとインターフェース設計にあります。たとえば、
- マーケティング部向けには「SNS投稿文・記事構成・広告文生成」
- 人事部門向けには「求人票作成・面接質問生成・応募者スクリーニング」
- 営業部門向けには「商談議事録・顧客向け提案資料の作成支援」
など、現場ニーズに直結したユースケースがあらかじめ整備されています。
さらに、導入企業側で新たな業務テンプレートを追加・編集することも可能で、カスタマイズ性と拡張性を兼ね備えている点も魅力です。
導入実績には、地方自治体・国交省関連機関・医療法人など、公共性・透明性・文書正確性が求められる現場が多数含まれており、その信頼性は折り紙付きです。
現場主導でAIを活用したい企業にとって、Graffer AI Studioはまさに“現場が自ら動かせる”生成AIの理想形と言えるでしょう。
▼Laboro.AI – 自社専用AIをゼロから構築するプロ向け解決型

「既製品のAIでは対応できない」「業務フローそのものが独自すぎる」──そんな企業に選ばれているのが、Laboro.AIです。
Laboro.AIは、いわば“カスタムAIのオーダーメイド工房”。汎用的なAIプラットフォームではなく、企業の業務フロー・データ構造・業界特性に合わせて、AIをゼロから構築するスタイルを採っています。
最大の特徴は、開発のスタート地点が「プロジェクト目標・業務課題の可視化」であること。コンサルタントが業務ヒアリングを通じてAI導入の狙いを明確化し、それに合わせて適切なAIモデル・処理構成を設計。単なるツール導入ではなく、“業務そのものの再設計”を含めたソリューションです。
導入事例としては、
- 製造業における品質検査の自動化(画像認識×熟練技能の学習)
- 不動産企業における顧客対応の自動化(FAQ分類と最適回答提示)
- 大手物流企業での配車最適化アルゴリズムの構築
など、通常の生成AIでは対応しきれない高精度かつ業界特化のユースケースが中心となっています。
また、AIを構築して終わりではなく、運用後のフィードバックと改善ループまで含めた「AIの育成支援」も含めて伴走する点が特徴。単なるAI導入支援企業ではなく、“業務改革パートナー”としての立ち位置を確立しています。
「既存のツールで限界を感じている」「中長期的にAIを戦略資産にしたい」と考える企業にとって、Laboro.AIはまさに、最上流から共に創る“自社専用のAI構築プロジェクト”の入り口です。
▼法人GAI – 高度なセキュリティとワークフロー連携に強いAI基盤

AIのビジネス利用が進む中で、「社内データの取り扱い」や「情報の安全性」を最優先に考える企業に注目されているのが、法人GAIです。
法人GAIは、業務支援AIとしては珍しく、RAG(検索拡張生成)+ ReAct(推論と実行の連携)という高度なアーキテクチャを標準搭載。これにより、社内ドキュメントやルールに基づいた精度の高い応答と、業務フローの自動化が同時に実現できます。
また、データの取扱いにおいても非常に厳格な設計がなされており、
- 国内サーバー上での運用
- 個人情報・機密情報のマスキング処理
- AI学習への非活用(完全クローズ型)
など、コンプライアンスが求められる業種(医療・金融・法務・官公庁)にも適応可能なセキュリティ基準を満たしています。
さらに特徴的なのは、社内における業務ワークフローとの結合性。既存のグループウェア(Microsoft365、Google Workspaceなど)や、業務アプリ(kintone、Slackなど)との連携機能を持ち、日々の業務プロセスに自然とAIが溶け込む設計になっています。
社内ポリシーが厳しい企業や、情報統制の強い大規模組織にとって、「導入して終わりではなく、“業務に根付かせる”AI」を求める声に応える存在。それが法人GAIです。
「AIを使いたいけれど、セキュリティと内部統制の問題で動けなかった」──そんな企業にとって、法人GAIは突破口になるAI基盤と言えるでしょう。
▼法人向け業務効率化AIツール比較表【主要6社】
| ツール名 | 提供企業 | 主な特徴 | セキュリティ対策 | 料金体系 | 代表的な導入企業・活用例 |
|---|---|---|---|---|---|
| JAPAN AI | JAPAN AI株式会社 | RAG搭載/業種別AIエージェント提供/多機能展開(CHAT・MARKETING・SPEECH) | 社内データ連携・アクセス制限・プロンプト支援 | 要問い合わせ | 広告設問の自動生成、議事録作成(マーケ企業など) |
| Autoron(オートロン) | ランサーズ株式会社 | 80種以上の業務特化アシスタント/Slack等との連携/プロンプト不要 | チケット制/限定環境内動作/利用ログ取得 | 月額2,000円/人~ | 社内業務の自動化(ログ分析、提案書補助等) |
| exaBase 生成AI | 株式会社エクサウィザーズ | 根拠資料付き回答/日本国内処理完結/部署ごとの権限設定 | 非学習設計/国内サーバー運用/部門別権限制御 | 要問い合わせ | 金融・医療・大手企業向け(セキュリティ厳格領域) |
| Graffer AI Studio | 株式会社グラファー | ノーコード操作/部署別テンプレ/官公庁導入実績あり | 内部展開型/プロンプト非依存/利用制御機能あり | 要問い合わせ | 地方自治体/行政支援機関/事務業務改革 |
| Laboro.AI | 株式会社Laboro.AI | 業務課題に合わせたフルカスタムAI/コンサルティング起点 | 設計段階から企業要件を組込/非汎用型構築 | PoCから段階見積もり | 製造・物流・不動産等での業務最適化実績 |
| 法人GAI | 株式会社ギブリー | RAG+ReAct対応/セキュリティ重視/マスキング機能搭載 | 国内完結処理/非学習設定/情報統制型環境 | 要問い合わせ | 清水建設株式会社など |
▼まとめ & 私の視点から見る「AIツール選定」

ここまで、法人向けに特化した生成AIツールを6つご紹介してきました。
- JAPAN AI – 総合型AIプラットフォーム
- オートロン – テンプレート型アシスタントの決定版
- exaBase – 根拠付きAIで高信頼
- Graffer AI – ノーコードで即現場実装
- Laboro.AI – フルカスタムのプロ仕様
- 法人GAI – セキュリティとRAGの両立
どのツールにも独自の強みがあり、自社の業務内容・体制・カルチャーによって最適解は変わります。
私自身が支援してきた中で確信しているのは、「選定は機能比較だけではなく、“誰が使い、どう定着させるか”が本質」だということです。
実際に多くの企業で「AIを導入したのに活用されない」という声が聞かれます。その原因は、ツールそのものではなく、導入から定着までを支える“設計と仕組み”の不足にあります。
この点で、私が日々活用・提案しているのが、弊社デジタルレクリムが開発したAIコレクションです。
AIの楽々フォン ― プロンプト不要、現場で即動くAI
AIコレクションは、プロンプトを書かずに業務で使える、完全カスタマイズ型の業務支援AIです。
- 導入企業の業務に特化(会計、営業、CS、管理など)
- 定例MTGと伴走支援により、現場にしっかり定着
- プロンプト不要で誰でも簡単に使える操作性
- ノーコードで修正・改善・成長が可能
まさに、「AIの楽々フォン」という言葉がしっくりくるような、誰でも、すぐに、業務の中で使えるAIツールです。
他社ツールに興味がある方でも、ぜひ一度、導入相談をいただければ幸いです。
▶ 生成AI導入の落とし穴とは?失敗しないための選定基準と注意点
よくある質問(FAQ)
Q1. どのAIツールが最も導入しやすいですか?
A. 導入しやすさで言えば、テンプレート型かつプロンプト不要な「オートロン」や「Graffer AI Studio」が特におすすめです。直感的に使えるUIとノーコード操作が魅力です。
Q2. セキュリティ重視で選ぶなら、どのAIツールが安心ですか?
A. 「法人GAI」や「exaBase 生成AI」は、国内完結処理・非学習設計・情報マスキング機能など、高度なセキュリティ対策を備えています。
Q3. 社内の複数部署で使えるAIはありますか?
A. 「JAPAN AI」や「法人GAI」は部門横断型に設計されており、FAQ・議事録・広告生成など多機能展開が可能です。
Q4. AI導入が初めての企業におすすめのツールは?
A. 初めての場合は「AIコレクション」や「オートロン」など、プロンプト不要かつサポート体制のあるサービスが安心です。